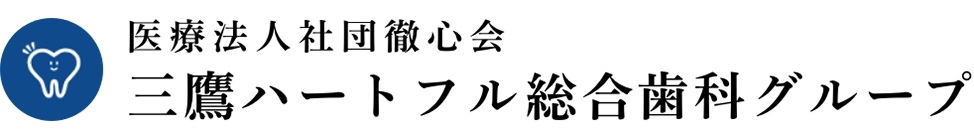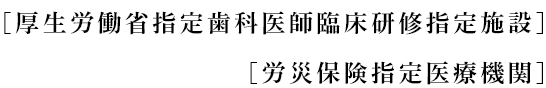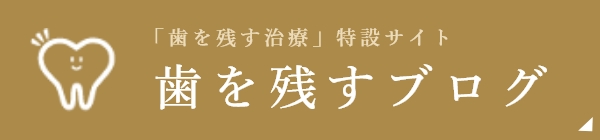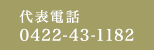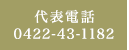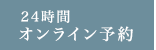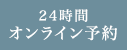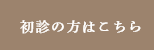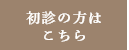セラミックのカラーコンセプト講義 —オールセラミック時代の審美を科学する—
1. はじめに:色を“感覚”で合わせる時代は終わった
近年、
原因は、“色”を言語化できていないことに尽きる。
実は、色は感覚ではなく科学。
そして、科学を知らないまま臨床に入ると、
私は十年以上前からこのテーマを外部セミナーで扱ってきたが、
当時は「色は技工士さんが決めるもの」という時代背景もあり、
多くの歯科医師が重要性を理解していなかった。
しかし、今は違う。
オールセラミック時代に入り、透明度・光透過性・
歯科医師側が色を理解していないと治らないケースが増えている。
だから今日、あえてこのテーマを改めて扱う。
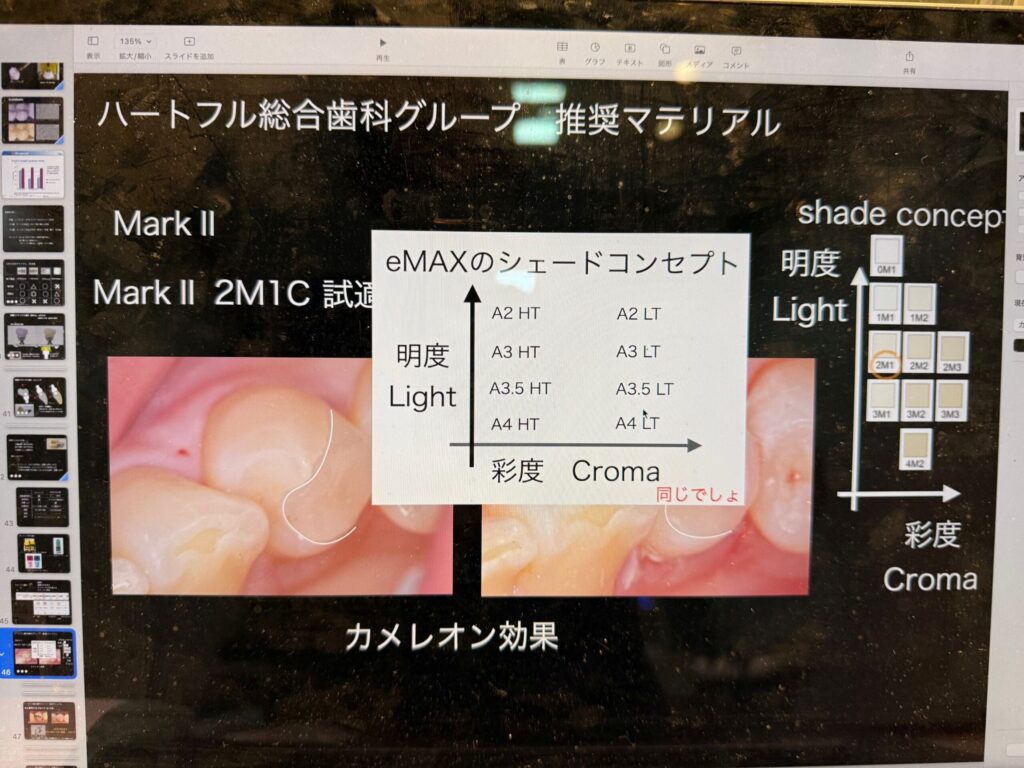
2. 過去のセラミック vs 現代のオールセラミック:何が変わったのか?
旧世代:メタルボンド(PFM)
- 金属フレームが下地に必要
- 色は“遮蔽+陶材の表面色”で作る
- 光透過性は低く、自然歯の深みが出にくい
- 技工士のアート要素が強く、再現性が難しい
現代:オールセラミック(ジルコニア/e.max)
- 高透過性
- 光は深く入り、内部反射により「生歯の奥行き」を再現
- 材料の層構造、セメント色の影響が大きい
- 科学的理解がないと狙った色にならない
特に違うのは、“
3. 色の本質:色相・明度・彩度からなる三次元空間
色を理解するには、HSV カラー理論が最も相性が良い。
● 色相(Hue)
赤・青・緑など“クレヨン的な色の違い”
→ 歯科ではほぼ固定(A系・B系など)
● 明度(Value)
明るい/暗い
→ 最も重要。1段ズレると“違和感の全ての正体”になる
● 彩度(Chroma)
色味の強さ(“A2 だけど黄色味が強い”など)
色は、
Hue(色相) × Value(明度) × Chroma(彩度)
の3軸空間で表現される。
これを理解すると:
- なぜ A2 と A3 の差が大きいのか
- なぜ明度が少し違うだけで“作り物感”になるのか
- なぜセメント色で Shade が飛ぶのか
すべて説明できる。
4. オールセラミック時代の“色差の正体”
① 光透過性(Translucency)
- ジルコニア:近年は高透過タイプの登場で天然歯に寄った
- e.max:透過性が高く、深部(歯牙色)からの色の“にじみ”
が発生
② セメント色の影響(Luting Cement Color)
オールセラミックは裏側からの光も拾うため、
セメントが“最終色の一部”になる。
白いセメント → 明度を上げる
濃いセメント → 深みが出るが暗くなる
透明 → 下地の影響を最も受ける
新人ほど軽視するが、実は Shade 選択と同じくらい重要。
5. なぜ大学では教わらないのか?
理由は単純で、
大学カリキュラムがオールメタル → PFM → デジタル の変遷に追いついていないため。
我々は10年以上前から CAD/CAM・オールセラミックを実臨床で積み重ね、
既に“実学としての色合わせ”を確立してきた。
6. ハートフルがやるべき教育の形
このカラー理論を理解すると:
- 色合わせの再現性が劇的に上がる
- 技工士との会話が「感覚」→「数値語」に変わる
- 修復物のトラブルが激減する
- 審美レベルが一気に底上げされる
教育こそハートフルの真髄。
知識の共有こそ組織の価値になる。
私は25年間の臨床で培ったセラミックの“本質”を、
これから新人教育に正式に組み込む。
それが結果的に、
患者様の笑顔につながるからだ。
7. おわりに:知識は時代を進める
歯科医療は、材料科学・光学・色彩学など、
異分野の融合で進化していく。
今日話した内容が、
スタッフ全員の“共通認識”として根付き、
より質の高い審美治療につながることを期待している。
私が語ることで、時代が一歩進む。
そして、この進歩はすべて
患者様の笑顔のために・・・
下田孝義